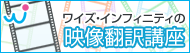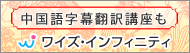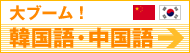現役字幕翻訳者 田中武人氏のコラム 第十一回
[2009-06-03]
第11回 「日本語にこだわる」
外国語の翻訳をやっているのであれば当然、語学力は必要です。しかし何語をやるにせよ、最終的には日本語にするのですから、日本語力が大事なのは論を待ちません。海外に長く滞在したからといって必ずしも翻訳がうまいとは限らない理由はこの点にあります。では日本語力とは何でしょう。それは、やたらと難しい言葉を知っていたり、「薔薇」を漢字で書けるような力ではありません。言いたいことを正確に、分かりやすく伝える能力のことだと思います。
「日本語が乱れている」というのは、いつの時代にも言われます。「ハンパない」「何気に」「キモい」などの若者言葉は論外として、レストランでの「コーヒーのほうはいつお持ちしましょうか」とか、コンビニなどでの「1000円からお預かりいたします」とか、電車の「ドアを閉めさせていただきます」などという慇懃無礼な表現は、いちいち気になります。新聞を読んでいても「事態が進展するかは分かりません」などという文章を読むと、トイレを出たあとで手を洗わなかったときのような気持ち悪さを感じます。「~するかどうかは分かりません」と書いてほしいのです。
字幕の場合は字数制限があるため、つい簡略表現やカタい漢語を使うことがありますが、不自然な字幕になりがちです。「見れる」「着れる」などのいわゆる「ら抜き」言葉は、今では人口に膾炙していますが、個人的には間違った用法だと思っています。これに対して「見ている」の代わりに「見てる」などという「い抜き」言葉は、間違いだとは思いません。話者のキャラクターによって使い分けるべきです。大御所の字幕でときどき見かける「~かもだ」「~せにゃ」などという表現は、若い翻訳者がマネすべきではありません。おかしいです。ところが最近は映画を観る観客のみならず、制作会社のディレクターでさえ、正しい日本語とそうでないものの区別ができない人がいるので困ります。
言葉の使い分けや表記についても神経質になります。「同志」と「同士」、「歯型」と「歯形」、「手当て」と「手当」などはそれぞれ意味が違います。「大通り」や「渡し舟」は漢字で表記しますが、「そのとおり」や「品物をわたす」は平仮名で表記します。「ウォッカ」ではなく「ウオツカ」、「ペンシルバニア州」ではなく「ペンシルベニア州」、「キャノン」ではなく「キヤノン」・・・枚挙に暇がない。
ところで字幕について、私はある法則を発見しました。原語が英語の場合、非常に大雑把に言って、原文の単語数と、それを日本語字幕にするときの文字数がほぼ一致するのです。つまり単語1つを日本語1字に置き換えることになります。たとえば、10単語で成り立っているセンテンスなら平均して2.5秒ぐらいでしゃべるので、字幕にすると10文字程度になるのです。こう考えると字幕翻訳というのは単語1つを1字で表すという、神をも恐れぬ所業を行っていることになります。ですから1字1字が砂漠の水の一滴のように貴重なわけで、たった1字変えただけで文全体の意味が変わってしまうこともあります。まさに「一事が万事」ならぬ「一字が万事」でしょう。その中でも特にカギを握るのは「助詞」と「語尾」でしょう。「私は会社に行く」と「私が会社に行く」ではニュアンスが異なりますし、「彼が言ったの」と「彼が言ったわ」も微妙に違います。あるいは「うまいだろう」と「うまいだろ」も差異があります。字幕翻訳者はこのような、重箱の隅をつつくような些事にこだわらなければなりません。
さあ、これを読んだあなたは明日から身の回りの日本語が気になってしょうがなくなるでしょう。特に字幕翻訳をやっていたり、これから目指す人は、常に日本語を鵜の目鷹の目で眺めてほしいものです。翻訳者というのは「日本語のプロ」なのですから。